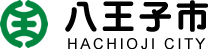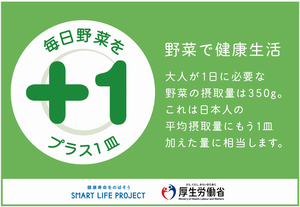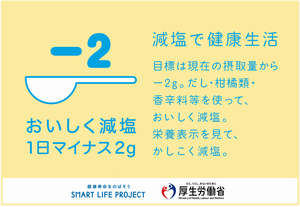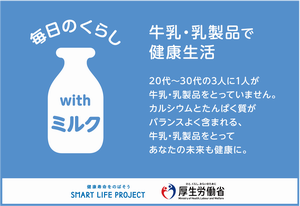毎年9月に食生活改善普及運動を実施しています
更新日:
ページID:P0032844
印刷する
食生活改善普及運動とは?

厚生労働省では、毎年9月1日から9月30日までの1か月を「食生活改善普及運動」の期間と
定めています。
令和7年度の食生活改善普及運動は、「まずは毎日、あと一皿ずつ野菜と果物をプラス」を
基本テーマとし、
● 野菜摂取量の増加
● 果物摂取量の改善
● バランスの良い食事を摂っている者の増加
● 食塩摂取量の減少
等に向けた取組について、更に強化するため全国的に展開するものです。
(参考)厚生労働省「食生活改善普及運動特設ページ」(外部リンク)
「スマート・ライフ・プロジェクト」(外部リンク)
毎日プラス1皿の野菜
厚生労働省が令和6年(2024年)から令和17年(2035年)まで展開する「健康日本21(第三次)」
では、成人1人1日当たりの野菜摂取目標量は平均350 g 以上としています。この数値は、循環器疾患や
がんの予防に効果的に働くカリウム、食物繊維、抗酸化ビタミンなどの適量摂取には、野菜350~400g
の摂取が必要と推定されることに基づいています。
しかし、令和5年国民健康・栄養調査によると、野菜摂取量の平均値は 256.0 g
(男性 262.2 g 、女性 250.6 g )であり、約95 g 不足している計算となります。
この機会に、野菜摂取を意識してみませんか?
八王子市のホームページでは、下記ページで野菜プラス1皿の方法をたくさん紹介しています。
(参考)野菜を食べよう!
毎日のくらしに果物を

しかし、令和5年国民健康・栄養調査によると、20歳以上の1日あたりの果物摂取量の平均は約93gと
目標値を下回っています。
果物は、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含みます。果物を十分に摂取することで、
おいしく減塩1日マイナス2g
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、成人1人1日当たりの食塩相当量の目標量は
男性 7.5 g 未満、女性 6.5 g 未満と設定されています。
しかし、令和5年国民健康・栄養調査によると、食塩摂取量の平均値は 9.8 g
(男性 10.7 g 、女性 9.1 g )と、目標値を上回っています。
例えば、買い物の際は食品パッケージに記載された栄養成分表示をチェックし、食塩相当量の
少ないものを選ぶことも減塩につながります。
八王子市のホームページでは、下記ページで減塩の方法をたくさん紹介しています。
(参考)なぜ減塩が必要なの?
毎日のくらしwithミルク
牛乳・乳製品には、骨や歯の形成に必要なカルシウムをはじめとする各種栄養素がバランスよく
含まれています。毎日、牛乳や乳製品を組み合わせて積極的に摂取しましょう。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(保健所)健康づくり推進課 健康づくり担当
-
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5112
ファックス:042-644-9100