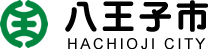- 現在の場所 :
- トップ > 観光・文化 > 八王子の歴史・文化財 > 関連文化財群「はちおうじ物語」 > はちおうじ物語其の五 主な構成文化財
はちおうじ物語其の五 主な構成文化財
更新日:
ページID:P0026915
印刷する
大久保石見守長安陣屋跡

〔小門町〕
![]()
大久保長安は、八王子城落城後に八王子宿の整備に関わり、現在の小門町から上野町に陣屋を置いて、関東十八代官の頭として関東幕領の統治を行いました。
石見土手

〔千人町二丁目〕
![]()
大久保長安が浅川の治水のために現在の並木町から元本郷町にかけて築いた町囲いの堤防です。長安の官途名「石見守」から「石見土手」と呼ばれています。現在は宗格院本堂の北側境内に、石積みを残しています。
≫石見土手
宗格院

〔千人町二丁目〕
武田家臣山本土佐忠玄(ただはる)の子、价州良天が文禄2年(1593年)に開いた寺院です。千人頭として八王子に移り住んだ父親の供養のために建てられました。千人同心組頭の松本斗機蔵墓(都指定旧跡)があります。現在は、「八王子八福神めぐり」の一つになっています。
追分の道標

〔追分町〕
文化8年(1811年)、江戸の足袋屋清八が、高尾山に銅製五重塔を奉納した記念に、江戸から高尾までの甲州道中の新宿・八王子・高尾山麓の3か所に立てた道標の一つです。甲州街道と陣馬街道の分岐点に建てられています。
新町竹の鼻一里塚跡

〔新町〕
![]()
八王子宿の東の入口に位置し、江戸から12里にあたるこの地に一里塚が建てられました。現在は付近で鍵の手に曲がる道筋が、昔の面影をわずかに残しています。
小谷田子寅の碑

〔下恩方町〕
![]()
小谷田子寅(こやたしいん)は千人同心で、特に医学に励み、薬を乞うもの、診断を求めるものがあとをたたず、民衆に慕われたといわれています。子寅の善徳を称え、同じ千人同心である塩野適斎が撰文し、植田孟縉が揮毫・刻字した貴重な碑です。
時の鐘

〔上野町〕
![]()
この鐘は、元禄12年(1699年)八日市名主新野与五右衛門を大旦那として、千人頭、千人同心をはじめ、近郷村々の協力により鋳造されたものです。約170年の間、八王子十五宿の人々に時を告げてきました。
千人頭の具足

![]()
八王子千人同心の組頭を務めていた旧家に伝来したもので、江戸時代中期のものと推定されています。現在は八王子市郷土資料館に収蔵されています。
旧甲州街道

〔東浅川町〕
東浅川町には、旧甲州街道に沿って千人同心家などの黒い板塀が残り、江戸時代の甲州道中の面影があります。
松姫尼公墓

〔台町三丁目〕
![]()
信松院にある松姫の墓所は、松姫の死後132年目にあたる延享5年(1748年)に千人頭たちが玉垣を寄進して現在のような姿になりました。
八王子千人同心屋敷跡記念碑

〔追分町〕
甲州街道の追分町交差点を陣馬街道に入ってすぐのところにあります。この辺りから甲州街道に沿って西の方に千人頭や同心の屋敷が建ち並んでいました。現在、この地に屋敷は残っていませんが、江戸東京たてもの園(小金井市)に「八王子千人同心組頭の家」が移築復元されています。
市守神社

〔横山町〕
![]()
天正18年(1590年)に、八王子開宿の功労者である長田作左衛門によって、市の商人の守護神として祀られたのが始まりです。江戸時代中期には、大鳥神社も合祀され、「お酉さま」「酉の市」と呼ばれる大鳥祭が現在も行われています。
≫市守神社
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生涯学習スポーツ部文化財課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7265
ファックス:042-626-8554
- 八王子の歴史・文化財の分類一覧